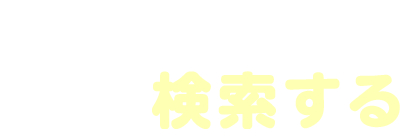福祉用具貸与(レンタル)とは!?介護保険の適用範囲を知っておこう
在宅で介護をしている人にとって、「福祉用具貸与(レンタル)」は非常に重要な選択肢といえます。
また、介護職として働いているなかで、利用者様やそのご家族からこの福祉用具貸与(レンタル)について質問されることもあるかもしれません。
そこで本記事では、福祉用具貸与(レンタル)の対象、福祉用具貸与(レンタル)と介護保険、福祉用具を借りたいと言われたときの対応について解説していきます。
福祉用具貸与(レンタル)の対象
福祉用具貸与(レンタル)は、「福祉用具はかなり高額なものであるうえに、状況が変われば使えなくなってしまう。また多くの物は使いまわしが可能であるから、『貸出』というかたちで利用してもらおう」という考え方から作られた制度です。
福祉用具貸与(レンタル)の対象となっているものは、11種類です。
- 車いす(その付属品)
- 特殊寝台(その付属品)
- 床ずれを防止するための道具(ウォーターマットなど)
- 体位を変換するための道具(空気パッドなど)
- 手すり
- スロープ(※工事が必要になるものは対象外)
- 歩行器
- 杖(※いわゆる「一本杖」は含まれず、松葉杖などの安定性の高いものに限られる)
- 徘徊感知システム
- 移動用のリフト(※工事が必要になるものは対象外)
- 自動で排泄物を処理する道具
どのような条件で何を借りられるかについては、次項で解説していきます。
福祉用具貸与(レンタル)と介護保険
福祉用具貸与(レンタル)は、無分別に行えるものではありません。
自費で借りる場合は自由に選べますが、介護保険を利用する場合は制限がかかることになります。
福祉用具貸与(レンタル)は、介護保険の適用内となります。
前項で挙げた11種類の福祉用具は、いずれも介護保険を利用して借りられる可能性があるものです。
ただし、すでに述べた通り、介護保険で借りられる福祉用具には条件があります。
要支援1・要支援2、そして要介護1の人が使えるのは、上で挙げた手すり・スロープ・自動で排泄物を処理する道具だけです。
それ以外の福祉用具は要介護2以上でなければ利用できません(自費であれば借りられます)。
介護保険が適用される福祉用具貸与(レンタル)の範疇は、「その道具がなければ、著しく生活が不便になり、生活が立ち行かないと認められるもの」「簡易な代替品では用をなさないと考えられるもの」にとどまります。
また、要支援・要介護状態であると認定された人の状態は、一定ではありません。
同じ要支援1であったとしても、AさんとBさんでは症状が異なるということもよくあります。
そのため診断の結果として、「要支援1の状態ではあるが、ほかの〇〇という福祉用具が必要である」と認められた場合は、保険対象内で福祉用具貸与(レンタル)をすることができます。
福祉用具を借りたいと言われたときの対応
ここでは、利用者様から福祉用具貸与(レンタル)を利用したいと言われたときの対応についてご紹介します。
まず、軽々にその場で「保険を利用して借りられます」と案内することは原則として避けた方が安全でしょう。
福祉用具貸与(レンタル)の利用においては、ケアマネージャーとの話し合いが必要になるからです。
独断で「保険を利用してレンタルすることが可能です」と言うのではなく、持ち帰って、他のスタッフと相談するようにしてください。
他のスタッフへの相談は、利用者様のためにもなります。
なぜなら、利用者様自身が自分の状態をきちんと把握できていない状態でも、専門の介護・看護・リハビリを担当するスタッフがフォローできるからです。
福祉用具は、自分に合ったものを使いやすいサイズで正しく使っていくことが重要です。
特に、杖などは微調整が必要になるものです。
このように複雑な福祉用具を、利用者様だけで決めるのは困難です。
そのため専門家たちがフォローして、その人に合う福祉用品を選ばなければなりません。
場合によっては、一度自宅に行ってみる必要もあるでしょう。
独断を避けてほかのスタッフに相談することは、具体的なフォローができることにつながります。
そして具体的なフォローは、利用者様にマッチした福祉用具を届けることにもつながります。
福祉用具をレンタルするという選択肢
福祉用具貸与(レンタル)は、利用者様・ご家族の金銭的負担や肉体的な負担を減らすための選択肢のうちのひとつです。
ただ、要支援・要介護度によっては介護保険内で借りられるアイテムに制限が出ます。
また、利用者様に合った福祉用具を模索する必要もあります。
そのため、福祉用具貸与(レンタル)についてご相談があった場合は、独断で判断せず、ケアマネージャーやリハビリ担当者、作業療法士などに相談することが重要です。