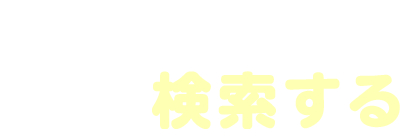体位交換は介護士の基本!負担をかけない体位の変え方
自分で体の向きを変えることのできない介護者様にとって、体位交換は重要な意味を持ちます。
また、体位交換は介護士の仕事における基本のひとつです。
本記事では「体位の変え方」について、基礎知識や具体的なやり方を解説していきます。
目次
体位を変える前に覚えておきたい準備と基本知識
まずは、体位を変える前に覚えておきたい基礎知識と、準備について解説していきます。
体位交換は2時間を基本とする
体位交換は、褥瘡(じょくそう)を防ぐために行うものです。
褥瘡は、体重で常に圧迫されている箇所の血行が悪くなって起こるものですから、体位交換を行い体重のかかる場所を変えることで予防できます。
そのため、2時間を基本として行います。
利用者様の状態と周りの状態を確認する
体位交換を行う前に、利用者様の体の状態を確認します。
まひがないか、排せつはどうかなどを見るようにします。
また、周りに邪魔な物があると体位交換の妨げになるので、こちらもチェックしておきます。
事前に声掛けを行う
介護の基本ですが、いきなり体に触れると利用者様はびっくりしてしまいます。
そのため、事前に必ず声掛けを行うようにします。
シーツはきちんと張るようにする
自分で体位を変えることが難しい利用者様の場合、小さなシワでも肌の刺激となります。
そのため、シワのないようにシーツを張るようにします。
負担の少ないやり方で行う
体位交換は、介護者の体にも負担をかけるものです。
そのため、ご利用者様ができる範囲で力を調整してもらいましょう。
また、利用者様の体とベッド(シーツ)の接着面積が少ないほど、体位交換は負担なく行えます。
さらに、必要に応じて福祉用具を利用します。
仰向け→横向きへの体位の変え方
ここからは、実際の体位交換のやり方について見ていきましょう。
いくつかのやり方がありますが、そのなかでも基本のものを紹介していきます。
なお、ここでの紹介は「右に向かせること」を前提とします。
1.介護者は、利用者様の右側に立ちます
2.利用者様の右手を曲げて、上に上げます
3.左側の足に、右足を乗せて足を組ませます
4.利用者の方と腰を手のひらで支え、介護者の方へ引き寄せます。これで横向きになります
以上の3ステップで行うのが基本です。
それでも体位が安定しないということであれば、クッションなどを利用します。
横向き→端坐位への体位の変え方
今度は、「座る姿勢(端坐位)」に持っていくための体位交換の方法を紹介します。
まずは、仰向けに寝ている利用者様をまず横向きにし、そこから端坐位に移行するようにします。
仰向け→横向けの姿勢の体位変換は前項で紹介しましたので、横向けになった状態からのものを解説します。
1.介護者の方向に向けて横向きになった状態から、右手を足に添えます
2.右足を用いて、足を地面側に下ろします
3.2の流れで左手で体を支えて、ゆっくりと起こします
こうすることで、利用者様を端坐位の姿勢に導くことができます。
「仰向け→横向け」への体位変換と、「横向け→端坐位」への体位変換は、体位変換のなかでも行う頻度が高いものです。
これらは利用者様のみならず、介護者にも負担がかかりやすいので、正しい姿勢と手順で行うことが大切です。
これによって、介護者の職業病である腰痛などのリスクを大幅に軽減することができます。
正しい手順と姿勢で体位交換をしましょう
体位交換は、介護職の仕事の基本となるものです。
2時間に1回の体位変換を心掛けましょう。
また、ご自身で体の向きを調整したり、体を起き上がらせたりすることが難しい利用者様にとっては、褥瘡を防ぐためのポイントともなります。
体位変換を正しく行うことで、介護する側の負担も大きく軽減することが可能です。