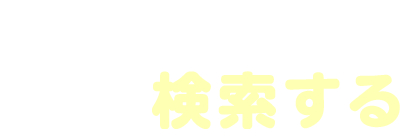介護タクシーとは!?介護保険適用と適用外のタクシー利用方法の違い
介護を必要とする人のためにある制度のひとつが、「介護タクシー」です。
これは非常に便利なもので、うまく利用することで介護を受ける人やそのご家族の負担を大きく軽減できます。
本記事では、「介護タクシー」について詳しく解説していきます。
目次
介護タクシーとは
介護タクシーとは、介護に使うことを目的としたタクシーです。
多くの場合、身体障がいを抱えている人や高齢者のためにスロープやリフトがつけられており、乗降・移動がしやすいようになっています。
この介護タクシーは、介護保険の対象となっているもの、対象にならないものに分けられます。
【介護保険適用】タクシーの利用方法
まず紹介するのは、介護保険が適用される方の介護タクシーです。
これは「通院等のための乗車または降車の介助」というサービスのもとで運営されているものです。
特徴として、介護タクシーを運転する運転手は「介護職員初任者研修(130時間の講習と筆記試験に合格することで取得できる)などの資格を持っている必要があります。
また、介護職員初任者研修などの資格を持っている運転手であるため、乗降の手伝いも行ってもらえます。
加えてカバーできる作業範囲も比較的広く、外出準備の手助けなども頼むことができます。
利用対象
介護保険の適用範囲で利用できる介護タクシーの場合、原則として利用できるのは、要介護者のみが利用対象者となります。
なお、保険適用範囲で利用できる介護タクシーの場合、要介護認定(1~5)を受けていることが条件となります。
加えて、ケアマネージャーとの相談で介護プランを相談しなければなりません。
カバーできる作業範囲は比較的幅広いものの、あくまで日常生活や社会生活を行う上で必要と認められる外出(通院・銀行での預貯金の引き出し・選挙など)、の場合のみ利用できます。
利用料金
料金は、時間制か距離制かによって異なります。
また明確に「〇キロ〇円」と定められているわけではありません。
ただおおむね、時間制の場合は30分ごとに1000円程度、距離制の場合は初乗り2キロまでが800円で1キロ走るごとに400円追加……といったかたちをとることが多いです。
また、乗降介助を受けると1回につき200円~300円程度、身体介護を利用すると250円~1000円程度かかります。
この部分は介護保険が適用となり、負担分も少なくなります。(上記の200円~300円、250円~1000円は自己負担額)
【介護保険適用外】タクシーの利用方法
次に、「介護保険適用外の介護タクシー」についてみていきましょう。
これは民間のタクシー業者などが運営しているものです。
最大の違いは、運転手が介護関係の資格を持っている必要はなく、また介助サービスは受けられないという点です。
「ストレッチャーやリフトがあるだけの、一般的なタクシー」と考えた方がよいでしょう。
利用対象
一般的なタクシーと同じ扱いですから、誰でも利用できます。
またご家族が一緒に乗ることもできますし、遊びの予定などで外出することもできます。
業者によっては介護のために必要な道具(車椅子など)を用意しているところもありますが、利用したい場合は事前に確認してください。
利用料金
一般的なタクシーと同じ料金形態をとっています。
時間制と距離制の2本柱であり、時間制の場合は30分で3000円程度が目安となります(時間が長くなれば割引が効くこともあります)。
距離制の場合は800円前後でしょう。
また、迎車料金が必要となることもあります。
介護タクシーについて正しく知ろう
体が不自由になると、どこかに出かけることも難しくなります。
そんな人の強い味方となるのが、「介護タクシー」です。
ただこの介護タクシーには2つの種類がありますし、どちらも利用するときには当然料金もかかります。
そのため、それぞれの特性を知ったうえで利用することが重要です。